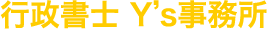少し遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。2026年も始まりはや1週間、年末年始休暇はあっという間に時間は経ってしまいました。年末年始は年始に毎年恒例の初詣に行って参りました。伏見稲荷大社に1日の夜に初詣に参拝してきました。
伏見稲荷大社は夜に行ったにも関わらず結構な人出で賑わっていました。参道に至る道に屋台で色々な物が販売されていて食べ物の色々な良い匂いがして活気があり良かったです。
3日の日には子供の頃からずっと参拝している乃木神社に初詣に参拝してきました。
7日に午後から、母校が全国高校ラグビー選手権の決勝戦に出場しておりましたので、テレビ中継もありましたが、わたしはネットでチラチラ見ながら陰ながら応援させていただきました。母校の結果は惜しくも敗れ準優勝という結果となりましたが、母校の後輩達の活躍には胸熱くなるものがあり、良い刺激となりました。また、気持ち新たに色々なことに挑戦したいという気持ちになりますね。
年末年始休暇についてお知らせします。
2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)の間、年末年始休暇のため休業させていただきます。
なお、新年は1月5日から通常業務となります。
師走になり、冬らしい寒さの日も増えてきた今日この頃ですが、2025年も残すところあと3週間あまりとなり、気ぜわしい日々ですが、今回のお話は、事務所HPや名刺にも記載している保有資格のAFPの更新手続きでのちょっとしたトラブルの話です。
事務所HPや名刺に保有資格AFPと記載しているのですが、AFPは更新完了後そのAFPライセンスカードが届くのですが、そのライセンスカードが届いていなかったのです。
7月末くらいか8月上旬に更新完了のハガキが届いていて、そこにはAFPライセンスカードは10月下旬に送付します。となっていたのですが、11月下旬になってもライセンスカードが届いてなかったのです。そのとき持っているAFPライセンスカードは11月30日までの有効期間となっていることから、それ以降の有効期限の更新後のAFPライセンスカードが欲しいところですが、まだ来てない、11月下旬に日本FP協会に問い合わせてみることにしました。電話で問い合わせると、何とかかんとかは1(イチ)を何とかかんとかは2(ニ)をみたいなよくあるフリーダイアルのコールセンター的なやつで、自分の用件は何番なのかを耳をすまして該当番号を押し、電話口に担当が受けてもらい、やっとこさこちらからの用件をAFP更新完了ハガキを見ながら、AFPライセンスカードは10月下旬に発送とのことですが、いまだに届いてません。とこちらが申しますと、会員番号等の照合とかをしてもらうと10月28日に発送しているというのです。毎日のようにポストの中を確認していますが届いてなかったと思うけどなぁ。まぁ、とりあえず届いていないので、AFPライセンスカードを送ってもらうことにしました。11月下旬にライセンスカードを送ってもらうお願いをして、1週間後を目処に届きますとのことでしたので、今までのように毎日ポストの中を確認をしてきました。1週間経っても届いていない、えっ!1週間経ったでと思いましたが、カード発行の日数もあるのだろうと思い、もう2、3日待ってみようとなり、AFPライセンスカードを送ってもらうことをお願いした日から2週間を経つ日には再度日本FP協会に問い合わせようと思っていたところ、もう今日ライセンスカードが届いてなかったら明日日本FP協会に問い合わせようと思っていたその日、外出先から戻ってきてポストを確認すると日本FP協会からの重要親展の封筒が入っていたのです。おっ!やっときたかと思いましたが、中身を確認するまでは安心できません。中身を確認すると、AFPライセンスカードがちゃんと入ってました。あぁ良かったと一安心でした。自身の事務所HPや名刺にもAFPと記載していますので、証明するものとして必要なので良かったです。
今回のように、その期日までにライセンスカードが届いてないだけの話でしたが、その後の手続きや不安は業務においてもそうだなと思わせるものでした。というのは相談を受けて、いついつまでに書類を送りますといった場合に、その期日にその書類が届いてなかったら、その後の手続きはどうなるの?ということになり不安になったりすることもあり得るなぁということを思いました。
臨時休業のお知らせです。
誠に申し訳ありませんが、都合により11月12日、13日を臨時休業させていただきます。
11月14日から通常業務となります。
10月下旬になり、やっと秋らしい気温になり過ごしやすい感じになってきた今日この頃ですが、秋の過ごしやすい日も長くはなさそうな時折、師走前くらいの気温で秋も短いような気がします。
さて、今回のお話は日常的に使っているPCの買い替えの話をしようと思います。夏くらいからWindows10は終了しますよというのをよく目にしていましたが、Windows 11に更新ということを自分の使用しているPCもしないとなぁ。と思っていましたが、時間もかかるだろうし、10月にまでしたらいいやと思い日々を過ごしました。9月下旬にPCをWindows 11に更新しようと試みようとした所、使用しているPCが更新対応しているかをチェックできるものがあり、それでチェックしてみると対応出来てないことが判明したのです。やばいと思い、Windows11に10月14日までに対応しないといけないということから、家電量販店に駆け込みPCを Windows11対応のものを購入してきました。
新しいPCを買ったら、始めにすることといえば、セットアップという面倒な作業ですよね、メカオンチな自分としてはちょっとした億劫な作業で、時間もかかるし嫌だなあと思い、しぶしぶ必要なことだからと割り切ってやっていきました。やっとこさセットアップが終えることができました。
以前まで使用していたPCと同じように使うためには少しの慣れと使用していたソフトやアプリなどを入れていかないとなぁ、とまだまだやる事がありますがぼちぼちやっていこうと思います。
今回のお話も業務には直接は関係ないお話でしたけど、業務に関わる興味深いトピックがありましたらまたお話させていただこう思います。
まだ夏のような暑いときもありますが、9月も下旬になってからやっと秋めいて来てようやく過ごしやすくなってきたなぁと思う今日この頃ですが、今回のお話は、前回と同様に業務とは関係のないお話となります。
先日、机の引き出しの中を整理していたら引き出しの中、日頃はあまり見ていなかった箇所からカードブックが出てきまして、そのカードブックって何と思われる方もおられると思いますので、少し説明しますと、名刺などの整理にしばしば使われるノート型のものでノートの1ページごとに何枚かクリアケースがあり、そこにカードや名刺を入れていくブックのことです。今回、出てきたカードブックを開いてみますと、子供の頃に旅先やお土産などで集めていたテレホンカードがありました。未使用のテレホンカードが25枚程見つかりました。穴の空いたテレホンカードも何枚かありましたけど、これは公衆電話が少なくなっている昨今ですが、災害時にでも役立つと思い取っておこうということにして。
では未使用のテレホンカードは使い道は、ネットで検索してみますと、買取店に持っていくといくらかには値段が付くみたいということが分かりましたので、買取店に一応持って行き買取をお願いしてみましたところ、1万円くらいの買取額になり、ちょっとした臨時収入になりました。何だか、整理も出来たし少しお小遣い的な臨時収入も得たし、プチラッキーって感じでした。
よくよく考えてみたら、買取店をハシゴして査定額を比較したらもう少し高く買取してくれる所もあったと思いますが、私自身の行った店で、最初の提示された額が私の思っていた額より良かったという点からその店で決断してしまいましたが、その点は、少し悔やまれますね。
今回のお話も、業務とは関係ないお話でしたけど、また、業務に関係する興味深いトピックがありましたらお話させていただこうと思います。
8月も終わりに近づいてきて、暦によれば秋になる9月の声が聞こえてくる今日この頃ですが、まだまだ残暑厳しい日が続きうんざりするときもありますが、今回のブログはまさにそのうんざりするようなお話を行政書士業務とは関係はありませんが、お話させていただこうと思います。
今年の梅雨は短く夏本番が早く訪れて本格的な暑さも早くやってきて夏の強い味方エアコンのお世話になるのが早い時期から長時間使用してました。この夏前くらいから暑くなってきていましたが、夏の真っ只中のある日、冷えが弱くなってきたなぁと感じてましたので、設定温度を一番下まで下げ、風量を強の最大にしてみたりしても、冷えなくなり、そういえばここ2、3年前くらいから少し冷えないなぁと感じてはいましたが、高い買い物なのでエアコンをエイヤッとは買い替えせず、だましだまし使用してきましたが、この夏はまだまだ残暑は続くと思い、今まで12年半程使用してきたエアコンはとうとう悲鳴を上げてしまいました。
ついに、エアコンの買い替えの決断をしました。決断したのはいいのですけど、決断したのはお盆休みの時期でした、お盆休み期間に家電量販店に行って、あまりに厳しい夏の後半にエアコンは在庫があるのか、在庫があってもすぐ買って、業者の方に取付設置してもらえるのか、と思いながら家電量販店に行き店の方とエアコンについて何せ高い買い物ですからあれこれ聞きまして、これだと思うエアコンに決めました。こちらとしては、気になる日程のことでしたが、お盆休み期間に店に行っていたことから、最短でも8月末か、9月の頭にエアコンの取付設置かなと思っていましたら、何とお盆休み明け、3日先からの日程で都合の良い日程で取付設置できますよという嬉しい返答がきました。そこで、こちらの都合の良いできるだけ直近の日に取付設置をお願いしました。
これで、無事にエアコン取付設置され、何とかまだまだ続く残暑にも強い味方になってくれそうです。
以上、夏のちょっとしたお話でした。
2025年8月13日(水)から16日(土)の間、夏季休暇のため休業させていただきます。
8月18日(月)から通常業務を行いますので、よろしくお願いします。
連日の猛暑が続いていて、暑さでバテてしまいそうな日々ですが、今回は、令和8年1月1日施行の行政書士法の改正について少し内容をご紹介しようと思います。
今回の改正は、次の5点の改正です。
1点目「行政書士の使命」
2点目「職責」
3点目「特定行政書士の業務範囲の拡大」
4点目「業務の制限規定の趣旨の明確化」
5点目「両罰規定の整備」
5点の改正がありますが、中でも3点目の「特定行政書士の業務範囲の拡大」が、行政書士ではない方にも大いに関わるであろうと思われますので、少し説明させていただきます。今回の改正では、特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、手続について官公署に提出する書類を作成できる範囲が、行政書士が「作成した」ものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に関するものに拡大されました。どういうことと思われると思います。
行政書士が作成した書類に限られていたのが今回の改正で
申請者本人が作成した(前段階で行政書士が関与してない)官公署に提出した書類に係る行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、その手続ついて官公署に提出する書類作成することができるようになりました。
ちなみに、当方も特定行政書士資格を有しておりますので、何かご相談があればご相談いただければと思います。少し早めの令和8年1月1日施行行政書士法の改正のご紹介でした。
今年の梅雨は短時間にざっと雨が降り、また晴れてメリハリのあった梅雨だったなぁと私的には感じた梅雨でしたが、近畿地方は例年にはないくらいに短さで6月の下旬には梅雨明けした模様とのことで、京都にも、うだる暑さが本格的にやってくると思いますと体調管理に気をつけて過ごさないとなと思う今日この頃ですが、
さて今回は、以前にも車庫証明の変更点について書いたのですが、そのときは、今年の4月から普通車の手続きに関する費用が車庫証明ステッカーの廃止によりステッカー交付代の510円が無くなり、手数料が2040円から2280円(京都府の場合)になりました。ということで費用の面では若干安く済むので良いですねと書いてました。
今回は、軽自動車はどうなの?と聞かれましたのでお答えしようと思います。なんと軽自動車については手数料の費用も発生せずに届出するだけということになりました。
以上、以前に書いた内容の補足といった感じでした。